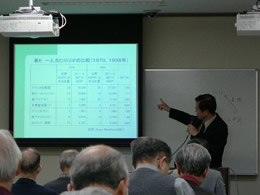第21回OFC講演会
演題
「『東アジアの奇跡』と資本主義の行方」
開催日時/場所
平成17年10月27日(木)午後6時半~ / 大阪大学中之島センター
講師
大阪大学大学院経済学研究科 教授 杉原 薫 氏

プロフィール
- 京都大学経済学部卒、東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得、経済学博士(東京大学)。
- 大阪市立大学経済学部助教授、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院歴史学部シニア・レクチャラーを経て、1996年より現職。
- 経済史の国際ネットワーク、GEHN (Global Economic History Network) の中心メンバーの一人。現在、社会経済史学会常任理事。
- 専門分野は近代経済史。アジアの工業化と国際関係の歴史的起源をグローバルな視点から追求している。
- 主要著書に『アジア間貿易の形成と構造』(ミネルヴァ書房:サントリー学芸賞、日経経済図書文化賞受賞)、『アジア太平洋経済圏の興隆』(大阪大学出版会)、編書に、『大正・大阪・スラム』(新評論)、『岩波講座 世界歴史19 移動と移民』、Local Suppliers of Credit in the Third World,1750-1960 (Macmillan), Japan in the Contemporary Middle East (Routledge), Local Agrarian Societies in Colonial India (Curzon), Japan, China and the Growth of the Asian International Economy,1850-1949 (Oxford University Press)など。
会場風景
講演要旨
1950年に東アジア10カ国(日本、NIES4カ国、ASEAN4カ国、中国)の世界GDPにおけるシェアは10パーセントだった。それが2002年には28パーセントを超え、いまなお増え続けている。他方、アメリカ、西ヨーロッパはシェアを落とした。旧ソ連地域のシェアは大きく落ち込んだ。東アジア以外の発展途上国のシェアは、全体としては停滞しているが、それは10カ国につづいて近年他の東アジア諸国や南アジアの成長が著しいからであって、発展途上国の過半は貧困にあえいだままである。要するに、この60年間は、経済成長の地域比較に関する限り、東アジアの「一人勝ち」だった。
しかも、それは、19世紀以来の西洋優位の世界経済の構造を大きく逆転させるものだった。20世紀前半まで、欧米先進国の世界GDPに占めるシェアは上昇傾向にあったのに対し、東アジアのそれは低下の一方だったからである。東アジアのなかで比較的成績の良かった日本ですら、一人当たりGDPで欧米にキャッチアップすることはできず、格差は一向に縮まらなかった。長い歴史的時間のなかで考えれば、ほとんど突然、しかも急速に、この傾向が逆転したわけである。「東アジアの奇跡」と言うにふさわしい事件だったと言えよう。
いったいどうして、他の地域ではなく、東アジアだけが高度成長に成功したのか。なぜそれは、それ以前ではなく、戦後になって一挙に達成されたのか。また、その国際的インパクトはどのようなものであったか。本講演では、近年のグローバル・ヒストリー研究を参照しつつ、その世界史的意義を考えてみたい。
西洋中心史観の意義と限界
資本主義の発達に関するこれまでの考え方には、 次の三つの要素を含むものが多い。第一に、17世紀-18世紀の科学革命や、それをもたらした合理主義、近代思想の評価の問題がある。日本、中国、インドなどでいかに前工業化期の経済成長(市場の発達、商業的農業の展開、プロト工業化など)が見られたとしても、抽象的な原理を適用した連続的な技術革新を誘発する社会的な土壌は、近世の西ヨーロッパではじめて形成された、とするこの考え方は、現在でも支持者が少なくない。しかしルネッサンス、宗教改革、主権国家システムの成立と産業革命の前提となる科学的技術的知識の蓄積にもかかわらず、1820年になっても、世界GDPの過半は中国とインドを中心とするアジアが作り出していた。一人当たり所得で見ても、18世紀後半の段階では大きな格差はなく、西ヨーロッパにおけるごく少数の先進地域で実質賃金が上昇したにすぎない。ヨーロッパ近代の果実を西ヨーロッパの大衆だけが享受しはじめたのは、これまで考えられてきたよりもはるかに遅く、19世紀になってからのことであった。
従来の理解の第二の軸は、19世紀から20世紀前半にかけて、イギリス産業革命に始まる工業化が、西ヨーロッパから世界に普及していった、とする理解である。技術、制度、規範のすべてにわたって、西洋が文明の布教者であり、自余の世界の歴史は、「ウェスタン・インパクト」(というのはいささか日本史的な表現だが)への対応として描かれてきた。近代経済史の教科書も、ごく最近までこのような発想をベースにして書かれてきた。しかし、このような理解には強い疑義が提出されつつある。はっきりしているのは、欧米列強による富の独占と技術的軍事的優位が確立し、帝国主義的な国際秩序が形成されたということである。それ以外の側面、例えば貿易、移民、通貨、金融などのグローバル化は、西洋と、アジアやその他の非ヨーロッパ世界との、双方の経済的知識やノウハウの蓄積の融合によって実現した。「西洋の優位」が確立した時代においても、キリスト教はもちろん、私的所有権の確立やリベラリズムのような西洋文明にとって基本的な要素は、文明を超えた合意事項とはならなかった。諸文明の多元的な価値が、工業化の強い普及力と帝国主義的な秩序のなかでぶつかりあい、消化不良を起こしながら、人類が大量の資本と資源を操ることができるようになった時代だったと言ったほうが事実に近いように思われる。
第三に、第二次大戦後、欧米列強の植民地支配の下にあった多くのアジア・アフリカ諸国が独立を遂げ、世界はアメリカのリーダーシップの下に、帝国主義的国際秩序から自由主義的国際秩序に転換し、世界経済と貿易の力強い成長を実現した、とする理解が重要である。冷戦の終焉とグローバリゼーションによって、世界は民主主義と経済的自由を軸とする体制に、イデオロギー的にも制度的にも収斂しつつあるとする、「収斂理論」もこの系譜で考えることができる。だが、戦後の世界経済の成長を主導したのは、決してアメリカだけではなかった。東アジアが冒頭で示唆したような未曾有の高度成長を遂げたのは、世界人口のごく一部が一人当たり所得を上昇させる従来のパターンではなく、膨大な貧しい人口を擁する東アジア地域全体の一人当たり所得が、急速に、持続的に上昇したからである。「東アジアの奇跡」の核心はここにある。国際秩序全体から見れば、アメリカの軍事的政治的経済的なリーダーシップが、東アジア諸国の成長イデオロギー、「開発主義」と結びついたことがそれを可能にしたと言えよう。
労働集約型工業化と人的資本の蓄積
それでは、東アジアの高度成長の内的要因としてはどのようなことが考えられるだろうか。戦後の日本は、いったん非軍事化、民主化を求められたが、中国共産化の影響もあって、すぐに工業力再建のチャンスが訪れた。そこで試みられたことは、欧米との圧倒的な技術格差の克服だった。しかし、単なるキャッチアップだったわけではない。日本は、戦前からの綿業や雑貨に加えて、造船、家電、自動車など、重化学工業のなかで比較的労働集約的な分野に次々と進出した。冷戦体制下のアメリカが軍事産業を含む、資源集約的、資本集約的な産業に特化しがちだったとすれば、日本は民需に特化しつつ、資源節約的、労働集約的な産業に進出したのである。軍事、航空機、宇宙、一部の石油化学などの分野では、急速なキャッチアップを放棄した。こうして新しい国際分業体制が比較的スムーズに成立した。つまり、戦後日本の復興と高度成長は、少なくとも結果的には、欧米との「棲み分け」によって可能になった。
労働集約型の工業化が東アジアに根づいた背景としては、通常は、土地や資源が稀少で、労働力が豊富だったという、いわゆる要素賦存上の特徴が指摘される。たしかに東アジアの小農社会に育った人たちは、資本と資源をふんだんに使って規模の経済を追求するチャンスには恵まれなかった。20世紀前半には資本と資源へのアクセスにおける西洋との格差はむしろ拡大した。しかし、労働力の質が劣っていたわけではない。仕事場で同僚と協調しつつ、問題に柔軟に対応したり、改善策を考えたりする能力は、労働集約型工業化の過程で広汎に形成された。
戦後の開発経済学の基本モデルの一つを作ったアーサー・ルイスは、発展途上国の農村に遊休労働力が豊富に存在する場合、これを生存費程度の賃金で利用することによって、工業化を進めることができると考えた。資本や資源の高価なところでは労働集約的な産業に特化できることを指摘していたとも言えるが、ルイス・モデルが労働力の質の向上への視点を欠いていたことは否定しがたい。農村から「無限に」供給されるルイスの労働力は、基本的には古典派経済学の想定した、同質的な「単純労働」を担う人たちだった。
しかし、持続的成長にとって決定的に重要なのは、労働力を拡大再生産しつつ、急速な技術革新や産業構造の変化に見合うように教育水準を上げ、同時にそのなかから成長の先端を担うエリートや技術者を育てていくことである。しかもその過程は、つねに一国で完結するわけではない。産業構造の高度化にともなって、基幹労働力が中卒から高卒へ、さらに大卒へと変化していった時、日本は「ワンセット主義」にこだわらずに、競争力を失った産業のリストラを敢行し、アジアの低賃金国との分業体制を模索した。追撃したNIESもまた、ASEANや中国の競争に直面した時、保護主義には向かわず、急激な産業構造の高度化に賭けた。
こうしてアジアは、低賃金労働力の裾野を広げつつ、同時にその中核に、教育水準の高い、良質の人材を形成することに成功した。東アジアでは、単に一人あたり所得が上昇しただけではなく、平均寿命と教育達成度においてもそれに対応する改善が見られ、生活水準の全般的向上が実現した。
資源節約型発展径路
先進国になった日本やNIESは、欧米のような資源集約的、資本集約的な産業に特化したのであろうか。端的に言えば、他のアジア諸国との関係では資本や技術に比較優位を求めるようになったが、アメリカのような資源集約的な産業に特化する方向には向かわず、資源節約的な技術を追求し続けた。これを資源節約型発展径路と呼ぶとすれば、この径路の発見によって、日本とNIESは、資源集約的なアメリカの産業とも、労働集約的な他のアジア諸国の産業とも、棲み分けることができたのである。
この径路の起源そのものは、日本では少なくとも徳川時代まで遡ることができる。しかし、資源の確保が日本にとって死活の問題となったのは、20世紀初頭における石炭から石油へのエネルギー転換の過程で、欧米のごく少数の企業の手に原油の供給が集中してからである。戦後も、中東原油の供給はメジャーに手に集中したままであり、原油の確保に必要な政治的軍事的判断も、欧米に依存せざるをえない状況が続いた。それでも、成長のためには物的インフラを整備しなければならない。比較優位のある産業だけでなく、素材産業や輸送部門も含めた経済全体へのエネルギー供給を確保しなければならない。こうして日本は、競争力の落ちた石炭を切り捨て、エネルギー効率の改善を図りつつ、中東からの原油の輸入に依存して成長する道を選んだ。ごく大雑把に言えば、NIESもそれに続いた。
石油危機の際にも、この戦略は揺るがなかった。そして、省エネ技術の発達に力を入れ、原油の絶対輸入量をあまり増やさずに生活水準を着実に向上させることに成功した。GDP当たりのエネルギー消費量では依然としてアメリカや多くのヨーロッパ諸国よりもはるかに低い水準を維持したまま、労働生産性や一人当たり所得ではそれらの先進国と肩を並べるようになったのである。1970年代以降、ドルで測った日本の賃金が急上昇し、労働集約的な産業の一部が他のアジア諸国へ移転するとともに、労働節約的、知識集約的な技術が意識的に追求されるようになった。資本の不足も解消された。しかし、日本とNIESは、資本集約的、資源集約的な技術革新の方向には向かわなかった。原油価格の高騰を背景に、資源節約的な技術を求める努力はむしろ強化されたように思われる。
もちろん、日本の場合、その直接の背景は資源の外国依存、とくにエネルギーの中東の原油依存にある。同じことはNIESについても言えよう。さらに、最近では中国も、資源、エネルギーの外国依存を急速に強めつつある。東アジアの高度成長が他の地域の資源、エネルギーの輸入に依存したものだったという事実は、それが決して域内の人々によってのみ達成されたものではなく、発展途上国を含む国際分業体制に深く依存したものだったことを示している。現在の日本は、なおエネルギー消費量の半分を原油の輸入に依存している。代替エネルギーの開発の努力にもかかわらず、東アジアのエネルギーの高い輸入依存度は簡単には低下しそうにない。
にもかかわらず、資源節約型径路の発見は、「東アジアの奇跡」の最良の帰結である。発展途上国が、地球環境問題に配慮しつつ工業化を進めるためには、今後、できるだけ労働集約的で、資源節約的な技術を取り入れる方向が望ましい。とくに中国が、日本やNIESのたどったこの径路に、いかに早く近づくことができるかは、世界経済全体にとってきわめて重要な問題である。
*この講演要旨は、講演者本人が講演の原稿をもとに作成したものです。