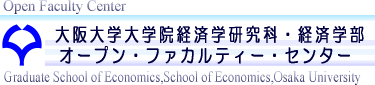
第30回OFC講演会
演題
「経済と倫理:アダム・スミスから学ぶ」
開催日時/場所
平成20年11月21日(金)午後6時半~ / ㈶日本教育会館
講師
大阪大学大学院経済学研究科 教授 堂目 卓生 氏

プロフィール
- 1959(昭和34)年生まれ。慶応義塾大学経済学部卒、経済学博士(京都大学)。
- 立命館大学助教授、大阪大学助教授を経て、2001年より現職。この間、サセックス大学およびロンドン大学客員研究員を歴任。
- 専門分野は経済学説史。
- 日本会術会議連携委員。
- 主要著書は、『古典経済学の模型分析』(有斐閣、1992年)、History of Economic Theory:A Critical Introduction (Edward Elgar、1994年)、The Political Economy of Public Finance in Britain 1767-1873(Routledge、2004年、日経・経済図書文化賞受賞)、『経済学―名著と現代』(共著、日本経済新聞出版社、2007年)。
- 訳書は、『リカードの経済学』(『森嶋通夫著作集6』、共訳、岩波書店、2003年)。2008年3月には、『アダム・スミス』(中央公論新社)を出版。
会場風景
講演要旨
アダム・スミスは『道徳感情論』(1759)と『国富論』(1776)を著した。『道徳感情論』は倫理学の、『国富論』は経済学の書物であるが、『国富論』の方がはるかに有名である。特に、『国富論』の中で1回しか言及されない「見えざる手」という言葉がスミスの名前と結びつけられ、スミスがあたかも市場原理主義者の元祖であるかのようなイメージが作られてきた。しかしながら、『道徳感情論』における議論を基礎として『国富論』を読むならば、これまでとは異なったスミスのイメージが得られるとともに、混迷する現代の市場経済において私たちが立つべき視座が与えられる。
『道徳感情論』の中核となる概念は「同感」である。同感とは他人の感情を自分の心の中に写し取り、それと同じ感情を引き起こそうとする人間の情動的な能力のことである。この能力を用いながら他の人びとと交流することによって、やがて私たちは自分の心の中に「公平な観察者」を形成し、それを使って自分や他人の行為の適切性・不適切性を判断するようになる。
胸中の公平な観察者は、他人の身体・生命・財産・名誉を傷つけること、つまり正義を侵犯することを是認しない。また胸中の公平な観察者は、不正な行為を受ける人の憤慨に同感し、そのような行為が処罰に値すると判断する。私たちは、この判断にしたがって正義の法を作り、それを遵守する。このようにして、社会秩序が形成される。
一方、世間(実在の観察者)は、大きな富や高い地位など目に見える快適な結果に高い評価を与える傾向をもつ。私たちは、世間から高い評価を得たいと願って富や地位を求める。富や地位への野心は人間の「弱さ」のあらわれなのであるが、勤勉、節約、創意工夫などを通じて経済を成長させ、貧しい人に仕事をもたらし、社会の繁栄に貢献する。しかしながら、野心は放任されるのではなく、正義感覚によって制御されなければならない。制御されない野心は、社会秩序を乱し、社会の繁栄を妨げるかもしれない。
『道徳感情論』で示されたスミスの人間観や社会観は、『国富論』に受け継がれている。たしかに、スミスは、市場において個人が自分の利益を求めて経済活動を行うことは、「見えざる手」に導かれて社会の繁栄を促進すると論じた。しかし、スミスの議論の背後には重要な留保条件がある。市場が社会の繁栄を促進するためには、個人の利益追求行動が正義感覚によって制御されなければならない。その場合、市場は自由で公正なものとなり、見知らぬ人どうしが必要なものを交換し助け合う「互恵の場」となる。
しかし、個人が正義感覚をなくして自分の利益を追求すれば、市場は不正と独占をもたらす装置となり、強い者が弱い者を傷つけ、食いものにする「戦場」になるであろう。スミスは、このような市場観から、独占の精神によって歪められた当時の経済体制、すなわち重商主義体制を批判し、自由で公正な市場の構築を唱えたのであった。
今後、金融市場を中心に市場に対する規制が強化されるかもしれないが、規制の強化だけで市場に対する信頼が取り戻せるとは思えない。市場がうまく機能するためには、ルールや規制だけでは十分とはいえず、むしろ市場参加者が自分の行動を胸中の公平な観察者の目で見て、その判断に従う習慣をつけていかなくてはならない。そして、そのような習慣は生きた人間同士の日常のつきあいのなかかで長い時間をかけて形成されるものである。したがって、市場に対する信頼を取り戻すためには、私たちはまず、スミスの市場観、すなわち、「自由で公正な市場は、個人の利己心によってのみ形成されるものではなく、同感によって、すなわち他人の感情を自分の心の中に写し取りそれと同じ感情を引き起こす能力によって支えられるものなのだ」というスミスの市場観を確認し共有するべきである。
*この講演要旨は、講演者本人が講演の原稿をもとに作成したものです。
