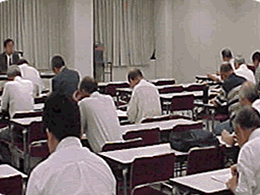第12回OFC講演会
演題
「戦前日本の研究開発体制―その特質と戦後への教訓」
開催日時/場所
平成15年8月8日(金)午後6時半~ / 梅田センタービル
講師
大阪大学大学院経済学研究科 教授 澤井 実 氏

プロフィール
- 国際基督教大学教養学部卒、博士(経済学、大阪大学)。
- 東京大学社会科学研究所助手、北星学園大学経済学部講師、大阪大学経済学部助教授を経て、1998年より現職。
- 専攻・研究テーマは近代日本経済史・経営史。特に、工作機械・鉄道車両・造船などの機械工業史、ブラシ・貝ボタン・琺瑯鉄器等の雑貨工業史、1930-40年代の科学技術政策史、工業化過程における技術者の役割、近代大阪の中小企業史などを研究。
会場風景
講演要旨
はじめに
現在、日本の経済はここ10年以上長い不況にあえいでいる状況で、少なくとも明治以降、これだけ長い不況というのを一度も経験していません。そこからの脱出ということが官民あげて大問題になっていますが、少なくとも一ついえることは、新しい産業の勃興や研究開発をベースにした新しい商品の登場、拡大がない限り、ちがった局面には移らないということです。そういう昨今の議論に刺激されまして、一度、戦前あるいは戦時中の日本の研究開発が実際どういうものだったのか。もし今のわれわれがそういった先人の経験から学ぶことができるとしたらそれは何なのか、そういうことを少しお話ししてみたいと思います。
今日は、特に第1次大戦あたりから太平洋戦争が終わるころまでの話を集中的にお話してみたいと思います。
私はやはり第1次世界大戦の前と後で日本の社会や経済は随分変わったのだろうと思います。第1次大戦の戦場はあくまでもヨーロッパでした。日本から遠く離れたヨーロッパで4年ほど続いた戦争が、なぜ日本の社会、経済にとって大きな意味を持ったのか。私は2つあると思います。一つは、戦争の長期化です。始まったときには数ヶ月で片が付くと思っていたのが、結局1914年の夏に始まり18年の冬までかかった。そこで日本が、日本の陸海軍が一番痛感したことは、この戦争というのは、今まで人間が経験してきた戦争とは格段に違う戦争だということです。日本史で最大の戦争である関ヶ原の戦いで東西あわせて百万に近い人間がぶつかったとしても、あの戦争は一日で終わったわけです。それが4年近くかかるということですね。つまり戦(いくさ)とは、それまではお互いに戦う両方が兵力を蓄え、それがぶつかり合って決着がつくというものだったのが、第1次大戦のような長期戦になると、戦場で戦争を継続するためには、片一方で戦場の反対側にある銃後で経済を拡大しつづけないといけない。経済ということと戦争ということが切り離された話ではなく、経済力に勝るものが軍事の帰趨を決するということを思い知らされた。「総力戦」です。「総力戦思想」というものを初めて日本は思い知らされたのだろうと思います。その世界戦争を日本は横目でみて、将来もし日本で起こった場合、今から備えをしておかない限り安心できないということを陸海軍、あるいは当時の内閣は痛感することになります。
もう一点は、戦争に全力を注いでいるドイツやイギリス、アメリカからの日本への輸入が止まり(あるいは遅延し)、代わりに自前で機械類や医薬品、染料などを用意せざるをえなくなったことです。武田薬品が本格的にその研究開発体制を整備し医薬品の研究開発に踏み出すのもこの時期になるわけです。戦前最大の研究機関「理化学研究所」のできるきっかけも、輸入が途絶する中でなんとか輸入代替を果たさないといけない、そのためには基礎研究をおろそかにできないのだという発想からでした。また当時、日本の紡績会社が使う紡機はほとんどイギリスのプラットという会社から買っていましたが、紡績機械を注文したのになかなか来ないわけです。結局プラットの紡績機械が日本にやってくるのは戦争が終わり景気が悪くなってから。必要のなくなった機械をどうするのか大問題になりました。結局その機械は上海に持っていき、中国に直接投資をして、日本の紡績工場をその機械を使って立ち上げていくきっかけになっていったわけです。
日本は明治以来、営々と西洋の先進工業諸国にキャッチアップする努力をしてきたわけですが、約半世紀の努力の末にたどり着いたレベルがどの程度のものであったか、第1次大戦によって痛感させられたわけです。大きく進歩した面と未だ足らずの両面を痛感させられた。模倣だけでなく自力で物を作っていくという努力を集中的に行わない限り、こういった事態はまた来るかもしれない。第1次大戦期は、日本の政府や民間企業、あるいは帝国大学が、日本人による新しい研究開発を行う体制を本格的に組み始めた時期と考えられるのではないかと思います。
1.技術者数の変遷
次に技術者数の変遷をみてみましょう。明治23年に高等教育を受けたエンジニアは日本に全部で500人しかいませんでした。民間だけでは182名しかエンジニアがいない、こういう国がそれから半世紀後の太平洋戦争真っ最中、1942年には6万人の技術者を要する国に変わっているのです。これはこの間の高等教育機関の拡張によります。
日本に帝国大学(東京、京都、東北、九州)が出来、第1次大戦が始まるときには4帝大に理工系の学部がすでにありました。高等工業は東京、大阪、熊本にすでにありました。京都工芸繊維大学の前身の京都高等工芸、それから名古屋、米沢、秋田(鉱山系の専門学校)、こういう学校から技術者を輩出する体制ができていたわけです。大正の半ばに、原敬内閣の政策で一挙に11の官立の高等工業が生まれたのです。また日本の植民地にも高等教育機関拡充の波は進んでいきました。
2.戦間期
(1)民間企業
こういったエンジニアの拡充を中心に、日本の研究開発が本格化していきます。当時日本は、繊維産業に非常に重きのある産業構成でした。日本の代表的な産業というと、紡績業であり、織物であり、製糸業です。しかしやはりまだ全体としては力がそんなについていなかった重化学工業、とりわけ金属や化学、こういった関係の企業に研究機関を設ける動きが目立ってきたと思います。当時日本でもっとも数の多い研究者を擁した研究機関を持っていた民間企業は東京電気、芝浦製作所といった会社です(昭和14年に両社は合併し東京芝浦電気、「東芝」になる)。
(2)官立試験研究機関
官立試験研究機関では、千人を超える職員を擁する機関が一つだけあります。当時所管は逓信省の「電気試験所」です。昭和9年で1090名の職員を擁し、年の研究経費が140万円という突出した研究機関です。その後、電電公社を経て現在のNTTの研究機関に移っていきます。「台湾総督府中央試験場」は、植民地、台湾の中央試験場ですが2百名を超す研究スタッフを擁する巨大な研究機関でした。それから「鉄道大臣官房研究所」。これは鉄道省の研究所で271名のスタッフを擁する鉄道研究のメッカでした。それから通産省の前身、商工省は東京と大阪に二つの工業試験所を持っています。こういったところが最先端テクノロジーの研究開発を担当しました。
(3)公立試験研究機関
昭和9年の時点で、ほとんどの府県では県立、府立の工業試験場がすでにできていました。持っていない県は1,2つ程度です。あとはすべての府県に工業試験場がある、そういう時代になっています。
公立研究機関でたぶん当時日本でもっとも先進的な府県は大阪府だったと思います。まず大阪府には国立の工業試験所があり、「工業奨励館」と呼ばれる大阪府立の研究機関があります。「大阪府立産業能率研究所」もあります。市立のものでは「大阪市立工業研究所」。こういった国立、公立の研究機関のネットワークができていきます。しかも、研究機関がそれぞれ競い合いながら、あるいは分業しながらその研究開発活動を行っているのです。また研究機関を持てないような中小企業を支援する活動を大正時代から大阪では行われてきました。現在と非常に違いますが、研究所の職員、府や市の公務員が研究活動を行うだけではなく、実業学校の教員が同時に研究所の嘱託となって研究活動を行う仕組みもこの時代にありました。
公立の試験研究機関は地場産業の育成に非常に貢献しました。国立や帝国大学の華々しい研究活動も大事ですが、同時に草の根の、地方で展開されていた研究開発も非常に大事ですし、日本的な特徴であろうと思います。
このように研究開発体制を大正期からだんだんと組んでくるわけですが、問題もありました。大きくいえば二つ。一つには民間の研究機関について、研究する部署と生産する部署の距離が離れすぎているということ。研究開発を行う人間は、研究開発だけやってそれがどういう新製品開発に結びつくのかということについて無頓着すぎると。もう一つは国立の研究機関に対してです。研究の成果を論文にまとめることに非常に関心があって、民間企業の育成という面ではほとんど連絡がない。産業界と国立の研究機関の関係が非常に弱いじゃないかという批判です。この二つが問題として指摘されました。
3.戦時期
戦争の時代に入ると、随分変化していきます。日本はますます軍需生産に偏っていかざるをえませんので、たとえば民間の企業で言うと戦争に関連する企業が爆発的に大きくなります。昭和18年頃、太平洋戦争に勝利するためには五つの産業をなんとか拡大しないといけないということで「五大重点産業」と言われました。石炭産業、鉄鋼業、軽金属(アルミニウム)、造船、航空機。この五つの産業を育成していくことが喫緊の課題であると言われました。昭和19年くらいからは、航空機の増産こそ戦争経済の焦点だということになります。さらに劣勢になった戦局を一挙に挽回するためには、どうすればいいか。自覚されたことは、レーダー(当時は「電波兵器」)の生産において、日本は決定的に劣っているのだということです。電波兵器のレベルアップが叫ばれるようになり、そういった産業、兵器関連の企業が一気に拡大していきます。
とにかく日本の持てる力を全部発揮して戦争に対処しないといけないということで、太平洋戦争中に盛んに強調されたのが共同研究です。当時は民間企業なら民間企業だけ、国立なら国立の研究機関だけ、軍はもちろん軍の研究機関で秘密裏にいろんなことやっていました。たこつぼ式に研究開発をやっていても非常に限界があると。そういった所属を超え、ある統一的なテーマのもとにみんなが集まり、たとえば東芝の研究員と帝国大学の工学部の先生と電気試験所の技師と、そういった人が一堂に会して共同研究をやることによって、レベルの高いものを生み出さないといけないのだという発想に徐々に変わっていきます。
財団法人大日本航空技術協会、研究隣組、戦時研究員制度、学術研究会議、日本学術振興会。こういった制度・機関はすべて、共同研究を行うために活動を行った有名な制度・機関です。
「研究隣組」についてですが、たとえば、レーダーの開発において日本は非常に遅れていると。するとレーダーの開発をするため東京帝大、京都帝大の先生、日立製作所の研究員、それから電気試験所の人が一堂に会して、共同研究を集中的に行いました。ある特定のテーマで括り集まって研究することを「研究隣組」と呼んだわけです。昭和17・18年度だけで70組が設立され、千人を超える科学技術者がそれに動員されました。戦局が絶望的な状況になる中で研究隣組は作られました。
最後に一つだけ引用しておきたいのですが、特攻隊が組織されるような押し迫った時期に科学技術を振興するために作られた技術院という中央官庁がありました。その技術院の総裁を務めた方に八木秀次先生がおります。あの八木アンテナの八木先生です。八木先生が技術院総裁だった昭和20年1月、衆議院予算委員会の席上で三木武夫氏が質問に立ちます。特攻隊を出すようなことでなく、戦局を一気に挽回できるような決戦兵器は出ないのかという質問で、技術院総裁に詰め寄るわけです。それに対して八木総裁はこう答えます。「必死でなくして必中であるという兵器を生み出したいことは、我々かねての念願でありましたが、これが戦場において十分に活躍いたしまする前に、戦局は必死必中のあの神風特攻隊の出動を待たなければならなくなったことは、技術当局といたしまして誠に遺憾に堪えない、慚愧に堪えないところで、まったく申し訳ないことと考えております。一日も早く必死必中ではなく、必中の兵器を生み出さなければならぬと考える次第であります。わが国の科学技術陣はすでに相当久しき以前から献身的な努力をいたしておりまして、その成果は大いに見るべきものがありと私は判断しておるのであります。遺憾ながらそれが最後の姿において必死ということではなくして、見事に敵を撃滅するという成果を発揮するに至っておりませぬことは、まことに申し訳なく思う次第であります」。
このときに八木先生の頭の中にあったのは![]() 兵器の開発のことです。決戦兵器の「け」をとって、当時は丸ケというふうに呼んでいました。特攻隊で突っ込んでいくのではなく、敵が動いたら、その動いたとおりに熱源を探知して追いかけるというミサイル攻撃の準備を日本はしていました。このために官民挙げた共同研究が行われました。そしてこの研究の開発途上で終戦を迎えます。これはあまり知られてないかもしれませんが、ソニーの盛田さんと井深さん、あのお二人が初めて出会われたのも
兵器の開発のことです。決戦兵器の「け」をとって、当時は丸ケというふうに呼んでいました。特攻隊で突っ込んでいくのではなく、敵が動いたら、その動いたとおりに熱源を探知して追いかけるというミサイル攻撃の準備を日本はしていました。このために官民挙げた共同研究が行われました。そしてこの研究の開発途上で終戦を迎えます。これはあまり知られてないかもしれませんが、ソニーの盛田さんと井深さん、あのお二人が初めて出会われたのも![]() 開発の研究が進められていく中でした。
開発の研究が進められていく中でした。
戦時期の共同研究は、戦局を左右するほどの大きな成果を生まなかったと思います。しかし、何も日本の社会にインパクトを与えなかったというわけではないと思います。当時、戦争に勝つためという目的だったわけですが、初めて日本の研究機関で官民挙げた共同研究というものを経験しました。自分が所属しているたこつぼの組織の中に閉じこもって研究するのではなく、ちがう世界の人間と交流するということを、戦争という不幸な体験を経てですが、経験したというふうに思います。このことが戦後の産学協同研究を考えるときに、一つのルーツになったということをわれわれは覚えておいていいのではないかと思います。
もう一つは、あれだけ努力したにも関わらず成果はあまり生まれなかった。何が問題であったのか、当事者はよく理解していたと思います。その反省を持ちながら、アメリカの占領軍を迎え戦後改革が行われたのだと思うのです。戦後「民主化」というふうに呼ばれますが、もっと平たく言えば平準化を促したのではないかと考えます。たとえば官庁の研究所ももっと垣根を低くして、民間の研究機関とお互い研究者として交わりあう姿勢が見られました。戦争によって努力して得たもの、反面いろいろ問題があったことへの反省、この二つのことがない交ぜになって、戦時期の経験が戦後に引き継がれていったのではないか。戦後がそこから始まったのではないかと考えたいわけです。
おわりに―戦後への教訓
昭和20年代というのは、戦争が終わり、従来のしがらみが一気に崩れていく中でそれまで言えなかったことが一気に言える世の中になりました。そこでひとつ気がつくのは、研究開発だけでなくいろんなところで担う人間がとにかく若いということです。少なくとも歴史の営みをたどっていったときに感じることは、このような時代の創造性の高さです。幕末維新期も第2次大戦の直後期というのもそういう時期ではないかと思います。もうひとつは、戦争中はその目的のためにすべての資源が投入されたわけですけれども、今はもちろんそういう方向性ではありませんが、若い科学技術者が懸けるに値するような研究テーマは何かということです。一生を懸けるに値するような研究テーマを見つけられるかどうか、それを支援するということは具体的にどういうことなのかを考えていくということは、中国の工業化やNICS、NIESの追い上げにおびえるよりは、はるかに生産的な姿勢なのではないかというふうな気がいたします。
最後のほうは、少し歴史屋の領分を逸脱したようなことを言ってしまいましたけれども、この辺でおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。
*この講演要旨は、OFC事務局の責任で編集したものです。